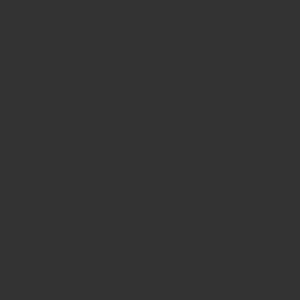シンガポールは世界銀行の「ビジネスのしやすさ」ランキングで常に上位に入るほど起業しやすい国です。
安定した経済環境と低い法人税率(17%)などの優遇された税制により、多くの外国企業にとって魅力的な拠点となっています。
本記事では、日本人起業家がシンガポールで会社を設立する際に知っておくべきポイントを、具体的な手順から必要書類、税制上のメリット・デメリット、注意点について解説します。
シンガポール発展の理由 シンガポールは世界で最も経済的に成功している国の一つと言えます。たとえば、以下のランキングに見て取ることができます。 世界競争力報告(世界経済フォーラムWEF) ランキング世界1位(2019年度、前年は2位)。「[…]
会社設立の具体的な手順
以下のステップにより、シンガポールで会社を設立することができます。
ビジネスのしやすさを重視するシンガポールらしく、会社設立はスムーズに行えることが通常です。
法人形態の選択:
まず事業内容や規模に適した法人形態を決めます。以下の形態が一般的です。
・有限責任会社(Private Limited Company)
・支店(Branch Office)
・駐在員事務所(Representative Office)
日本本社の一部門とする支店形態も可能で、シンガポール法人の赤字を本社の利益と相殺できるなどのメリットもありますが、親会社の財務情報を開示しなければならないなどデメリットもある点に注意が必要です。
外国のスタートアップや中小企業や外国企業の子会社には、柔軟性が高く運営コストも低い有限責任会社(Private Limited Company)が適しています。
法人形態の選択にあたっては、資本金要件や規制の適用範囲が異なるため慎重に検討が必要です。
会社を新しく設立する際に、その出資者(株式保有者)を個人とするか、法人とするか検討する必要があります。 特に日本企業がシンガポールで会社を設立する場合は、日本本社がシンガポール子会社に出資をするか、またはその日本企業のオーナーが直接[…]
会社名の登録
次に会社名を決めて、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)で名前を予約・申請します。社名は既存企業と重複しないユニークなものでなければならず、また不適切な語句(センシティブな単語や特定業種を示唆する語、有名企業と混同するような会社名)は却下、または保留され承認まで時間がかかるケースがあります。複数の候補名をいくつか用意しておくと良いです。
社名申請はオンラインで行い、通常1〜2営業日で承認がおります。申請費用は15シンガポールドル(約1,500円)程度です。
会社設立の申請(登記)
会社名が承認されたら、正式に会社設立登記を行います。これは会計企業規制庁(ACRA)のオンラインシステム(Bizfile+)から申請可能で、必要情報と書類を提出します。準備すべき主な必要書類は以下の通りです。
・会社定款(Company Constitution)
・株主リストおよび持株比率の詳細
・取締役全員のパスポートコピーと住所証明書(例:公共料金請求書など)
・少なくとも1名のシンガポール居住取締役の就任同意書
・シンガポール国内の登録オフィス住所情報
提出後、特段の問題がなければ1~2営業日ほどで登記完了となります。
設立費用は300シンガポールドル(約3万円)で、オンライン決済となります。
登記完了時には設立証明書(Certificate of Incorporation)法人番号(UEN: Unique Entity Number)が発行されます。このUENは税務申告や各種手続きで公式に使われる会社識別番号で、シンガポールで事業運営をしていく限り付き合っていく大事な番号となります。
銀行口座の開設:
会社設立後、事業に必要な銀行口座をシンガポールで開設します。主要メガバンク(DBS銀行、OCBC銀行、UOB銀行など)では外国法人に対応した口座開設サービスがあります。
開設時には、設立証明書、取締役の個人証明書類、株主リスト、定款などを提示します。手続きには通常1~2週間を要し、通常、口座開設には取締役の一人が現地で対面による手続きを行う必要があります(各銀行のKYC -know your clientのため)。
開設のために日本から渡航して手続きを行うか、シンガポール在住の協力者に同行してもらうケースもあります。近年ではマネロン対策から銀行口座開設に時間がかかるようになっており、適切に対応しないと開設を拒否されるケースもあります。
必要書類と法的要件
上記の手順でも触れましたが、シンガポールで会社設立する際に求められる必要書類と法的な要件について整理します。
取締役・株主に関する書類
全取締役と株主の身分証明(パスポートコピー)および住所証明書類が必要です。日本人起業家の場合、自身が取締役に就任するならパスポート及び居住証明(住民票の英訳または公共料金の英文領収書など)が求められます。
株主が法人(日本の会社)の場合は、その法人の登記簿謄本英訳や定款英訳など追加書類が必要になります。
現地取締役の選任:
シンガポール会社法上、少なくとも1名の取締役はシンガポール居住者である必要があります。シンガポール居住者とは、シンガポール国民・永住権者、またはシンガポール滞在ビザを所持者するシンガポールに居所がある者です。
日本人のみで会社を設立する場合で、日本人が現地に居住しない場合は、会計事務所など専門サービス業提供する現地の名目ディレクター(Nominee Director)を利用する必要があります。取締役に現地の人が入らない場合は、会社設立後日本人がビザを取得して自身が居住者となるまでの措置として通常利用する必要があります。
登録住所(オフィス住所)
設立時にシンガポール国内の住所を登記する必要があります。自前のオフィスをまだ持たない場合、バーチャルオフィスやシェアオフィスの住所を利用することも可能です。
ただし一時的な仮住所は認められず、郵便物を受け取れる正式な住所でなければなりません。住所要件は厳格で登記後も当局から郵便が届くため、信頼できる住所を確保しましょう。
カンパニーセクレタリー(企業秘書役)の任命:
シンガポールでは、会社設立後6ヶ月以内に企業秘書役(Company Secretary)を任命する義務があります。
企業秘書はシンガポール居住者である必要があり、会社の法定記録管理や年次報告提出を担います。一般的に、設立を代行するサービス企業が秘書役も兼任するプランを提供しているため、それを利用するとよいでしょう。
その他の基本要件
シンガポールは、現地パートナーがいなくても外国人100%出資、外国人株主1名での設立も認められます。最低資本金は1シンガポールドルから可能で、払込資本金額も登記時に決めます(事業に必要な運転資金を踏まえ適切に設定してください)。ただし、法人から日本人等外国人の就労ビザを申請する場合は、最低50,000ドル程度の資本金を設定する必要があります(事業運転資金や給料の支払いが可能か見られるため)。
シンガポールのビジネス規制
シンガポールはビジネスフレンドリーな国ですが、運営する上で遵守すべきビジネス規制や留意点も存在します。
外資規制の緩さ
基本的にシンガポールは外資に対して開放的で、業種による外資規制はほとんどありません。外国人が株主・経営者でも内資企業と同じ扱いで事業を営め、資本の国外送金も規制がなく、利益の本国送金に対する制限もありません。これは日本企業にとって大きな利点です。
年次報告と会計監査
シンガポール企業は毎年、決算日後7ヶ月以内にACRAに対して年次申告(Annual Return)を提出し、事業の概況や取締役・株主の構成を報告する必要があります。また会計年度ごとに財務諸表を作成し、原則として決算日後6ヶ月以内に定時株主総会(AGM)で承認を受けます。
ただし中小企業(売上高・総資産が各1,000万シンガポールドル未満、従業員50人未満など一定条件を満たす場合)は会計監査が免除されるため、監査人を置かなくても年次報告が可能です。これによりスタートアップ企業は監査コストを省けます。
会計監査とは シンガポールで事業を行う場合、現地の会計監査人の選任の要否について検討する必要があります。 ここで会計監査とは、企業が作成する財務諸表の適切性について、会社や利害関係者から独立した第三者が確認する業務をいいます。 会計監査の[…]
税務申告:
決算日後3ヶ月以内に仮納税であるEstimated Chargeable Income (ECI)の申告を行い、最終の確定申告は決算期から約11か月後が期限です。申告・納税を怠ると罰金や延滞利息が科されます。
シンガポール法人税申告の流れ 日本において法人税の申告は、原則として決算日後2ヶ月以内に提出する必要があります。(ただし、株主総会が決算日後3ヶ月目に行われるなどの理由で、実務上は3ヶ月末まで延長されることが通常です。) 一方、シンガポー[…]
雇用関連:
現地で従業員を雇用する場合、雇用法や労働ビザに関する規制を遵守する必要があります。シンガポール人・永住者を雇う場合は年金に該当するCPF(中央積立基金)への雇用主拠出金が義務付けられています。
外国人を雇用する場合は適切な就労ビザ(Employment Pass、S Pass、Work Permitなど)を取得し、定められた外国人雇用比率の範囲内で採用する必要があります。もっとも、高度人材の雇用に関しては比較的審査も迅速で、必要な人材を確保しやすい環境です。
コンプライアンスの重要性
シンガポール当局はコンプライアンス違反に厳格です。年次報告の未提出や法定書類の不備に対して罰金処分や最悪の場合法人の強制抹消(ACRAによる登録抹消)が行われることもあります。また、汚職防止法が厳しく施行されており、ビジネス上の不正行為に対する罰則も重いです。健全な内部統制と専門家の助言を得ながら事業運営することが求められます。
以上のように、シンガポールは規制面でも透明性が高く、基本的には遵守すべきルールが明確です。しっかりと法令を守りさえすれば、行政手続きやビジネス運営で過度な障壁に悩まされることは少ないでしょう。
シンガポール税制のメリットとデメリット(法人税・GSTなど)
シンガポールの税制は起業家にとって大きな魅力ですが、一方で理解しておくべき注意点もあります。ここでは法人税とGST(消費税)を中心にメリット・デメリットを見てみましょう。
税制のメリット
法人税率の低さ: シンガポールの法人税率は一律17%です。
日本の法人実効税率(約30%前後)に比べると大幅に低く、税負担を軽減できます。さらに中小企業向けの部分免税制度があり、課税所得の一部について実効税率を下げることが可能です。
シンガポールと香港は、アジアの金融ハブでビジネスの先進都市。さらに富裕層の資産が集積するウェルスハブでもあります。 金融やウェルスの中心となっている理由の一つがその税制と税率。以下の表のとおり、キャピタルゲイン課税、贈与・相続税が非[…]
スタートアップ優遇税制
設立したばかりの新興企業に対しては、最初の3年間にわたり一定額の所得まで法人税を免除・軽減する制度があります。具体的には、初年度から3年間で最初の10万シンガポールドル(約1,000万円)の利益に対して法人税が実質免除される優遇措置が用意されています(※条件により最大で最初の20万ドルまで約50%の減税)。この制度により創業期のキャッシュフロー負担を減らし、事業拡大に投資しやすくなります。
シンガポールは法人税率17%と、低税率国となっておりますが、原則として、決算日から2ヶ月以内に法人税の申告を行う必要があります。 シンガポールの会社法人税計算は、非常にシンプルです。日本ですと事業税や住民税などの影響があったり、複雑な調整[…]
配当・キャピタルゲイン非課税
シンガポールは単一課税方式(一段階課税)を採用しており、法人が利益に対して税金を納めれば、その後株主に支払われる配当には追加課税がありません。つまり受け取る配当金は非課税となります。またキャピタルゲイン(資本利得)課税が無いのも大きなメリットです。例えば事業売却益や株式譲渡益、仮想通貨売買益などは通常非課税扱いとなり、将来事業を売却して利益を得ても税負担が発生しにくいのです。
シンガポールで株を売った時は税金がかからない。 そんなイメージを持っている方は多いと思います。しかし、少し気をつけなければならない点も。 今回は、株式売却にかかる課税関係について解説したいと思います。 キャピタル・ゲインは原則、課税されな[…]
消費税(GST)の免税点
シンガポールのGSTは現在9%ですが、年間売上が100万SGD未満の事業者は登録不要なため、スタートアップ初期には事実上GSTフリーでビジネスを行えます。売上が成長してGST登録業者となった場合でも、課税仕入にかかったGSTの還付を受けられるため、最終的な税負担は売上に対するネット(差額)のみで済みます。
日本において、消費税率の引き上げは何かと話題になりますが、シンガポールにおいても同様の税制があります。その名もGST(Goods and Service Tax)です。 日本の消費税と同様、シンガポールのGSTも、物品・サービスの付加価値[…]
国際租税条約による二重課税回避
シンガポールは日本を含む80以上の国と租税条約を締結しています。そのため、シンガポールと日本双方で事業を展開する場合でも、同じ所得に対する二重課税を条約に基づき回避・調整することができます。例えばシンガポール現地法人から日本の親会社へ配当を送金する場合、条約により源泉税率の軽減や免除措置が受けられることがあります。
個人所得税との関係
シンガポール法人があげた利益には上述のように低い法人税しか課されませんが、日本居住の個人株主がその利益を配当などで受け取ると、日本の所得税・住民税の課税対象となります。つまり、日本に居住する起業家がシンガポールで法人を設立して利益を上げても、日本で合算課税されてしまう可能性があります(納税地によって異なるため税務専門家への確認が必要です)。
一方、起業家自身もシンガポールに移住し非居住者となれば、日本の高い個人所得税率(最高45%超)から離れ、シンガポールの低率な個人所得税(最高22%台)の恩恵を受けられるというメリットも生じます。
その他コスト面の留意
税負担が軽い分、シンガポールではオフィス賃料や人件費などビジネスコストが高めです。法人税メリットだけに目を向けると、現地での生活費・事業費の高さによって却って収益を圧迫される恐れがあります。例えば、シンガポールの物価・人件費は東京より高い水準にあるため(2023年時点で世界トップクラスの生活費)、節税メリットと事業コストをトータルで見極めることが大切です。
総じて、シンガポールの税制は「低い法人税+豊富な優遇措置」で起業を後押ししてくれる反面、事業が軌道に乗った際には消費税対応や日本との税務関係を考慮する必要があります。適切に計画を立てれば、税制メリットを最大限享受できるでしょう。
外国人起業家が注意すべきポイント
外国人、特に日本人がシンガポールで起業する際には、現地ならではの注意点があります。以下に主要なポイントを挙げます。
言語とビジネス文化
シンガポールの公用語は英語です。ビジネスは基本的に英語で行われ、日本語は通用しません。そのため、日本人起業家も英語で契約書や商談をこなす必要があります。
現地には中国系・マレー系・インド系など多民族が共存しており、多文化理解も重要です。意思決定のスピードや商習慣が日本と異なることも多いため、現地のビジネス文化に柔軟に適応する姿勢が求められます。
ネットワーキング
シンガポールで成功するには人的ネットワークが非常に重要です。日本人コミュニティも活発で、日本人商工会議所や各種業界団体が定期的に交流会を開催しています。これらに参加して情報収集や人脈構築を行うことで、現地の有益なビジネス情報やパートナーを得やすくなります。
また政府系機関(Enterprise SingaporeやEDBなど)主催のイベントや助成金プログラムも活用しましょう。シンガポール政府は外国スタートアップの誘致に積極的で、ピッチコンテストやアクセラレーター経由で資金・オフィス提供を受けられるチャンスもあります。
ビザと在留資格
日本人がシンガポールで経営に携わる場合、就労ビザを取得する必要があります。一般的なのはエンプロイメント・パス(Employment Pass, EP)で、会社の経営者や専門人材向けの就労ビザです。
EP取得には一定額以上の給与支給と十分な経歴・学歴が求められ、会社設立後にスポンサー(雇用主)として自社で申請します。もう一つは起業家ビザ(EntrePass)と呼ばれるもので、革新的なビジネスプランや資金調達実績を持つ創業者向けの特別なビザです。
EntrePassは給与要件が無い代わりに事業計画審査が厳しく、取得までに時間がかかる傾向があります。どちらにせよ、ビザ取得には数ヶ月を要することもあるため、起業計画と並行して早めに準備を進めましょう。
なお、ビザ取得までは前述のNominee Directorを立てて日本からリモート経営し、ビザ取得後に現地赴任するという段取りを踏む起業家も多くいます。
現地の生活コスト
シンガポールは世界でも有数の生活費の高い都市です。住居の家賃、水道光熱費、交通費、すべてが東京より割高な傾向があります。
「アジアの中の先進国」であるがゆえに人件費も高く、人を雇えば日本並みかそれ以上の給与水準が必要です。日本人起業家は自身と家族の生活費も考慮し、資金計画を立てる必要があります。
駐在員として企業から派遣される場合と異なり、スタートアップでは自腹で出費を賄うことになるため、予想以上に現地で資金が出て行く点に留意が必要です。
法律・契約面の専門知識
言語の項でも触れましたが、契約書や法律相談は現地の専門家(弁護士や会計士)に任せるのが安心です。会社設立時から信頼できる会計事務所や秘書役サービスと契約しておけば、年次申告や法改正への対応について適切なアドバイスが得られます。
特に日本とは異なる会社法・雇用法の下で運営することになるため、リスク管理の面でもプロのサポートを受けながら進めることをお勧めします。
以上の点を踏まえ、日本人起業家は「言語・文化の壁」「ビザ取得」「生活費負担」という3つのハードルに備える必要があります。しかしこれらは事前準備と現地リソースの活用で十分乗り越えられるものです。実際、多くの日本人がシンガポールでスタートアップを興し活躍していますので、心配しすぎる必要はないでしょう。
資本金・設立コスト・銀行口座開設手続き
起業にあたり気になる資本金や設立費用、および設立後の銀行口座開設について解説します。
必要な資本金
前述の通り、シンガポールでは最低資本金は1シンガポールドル(約100円)で会社を設立可能です。極端に言えば、1ドルを払込資本として登記すれば会社ができます。
ただし、実務的には初期運転資金として十分な額を資本金に充当しておく方が信用面でも好ましいです。例えばオフィス賃貸や従業員給与の支払いに備えて数万ドル~数十万ドル程度を用意し、それを資本金または開業後の運転資金とするケースが多いです。
なお、資本金額は設立後でも追加増資が可能なので、初期は必要最低限に抑えておき、事業拡大に応じて増やすこともできます。
設立コスト(費用)
シンガポールでの会社設立自体にかかる政府手数料はそれほど高くありません。会社名登録費用15ドル、設立登記料300ドル程度が主なコストで、合計でも数万円程度です。
ただし、多くの外国人起業家は設立手続きを代行サービス会社に依頼します。これら代行会社は、登記手続き一式に加え、現地取締役や秘書役の提供、住所貸与サービスなどをパッケージにしており、料金はプランによりますが数十万円程度を見込んでおいた方がよいでしょう。
例えば、Nominee Directorサービス込の1年間サポートパックで日本円にして20万~30万円前後が一つの相場です。もちろん自力で直接ACRAに申請することも可能ですが、言語面・制度面でのミスを避け迅速に処理するためにプロに任せる価値は大きいです。
銀行口座開設の手続き
シンガポールで法人口座を開く際の一般的な手順は、前述ステップでも触れた通りです。設立完了後、銀行に必要書類を提出し、KYC審査を経て口座が開設されます。
主要銀行ではオンライン申請の仕組みもありますが、実際には取締役や株主の身元確認面談が求められることが多いため、予約を取って支店に出向く必要があります。幸いシンガポールの銀行は英語対応がしっかりしており、日本語窓口を持つ銀行(例えば三菱UFJ銀行の現地法人など)もあります。
口座維持手数料は銀行によりますが月数十ドル程度、口座に一定の最低残高(数千ドル)が求められる場合もあります。昨今はFinTech企業によるオンライン専用口座(デジタルバンク)も登場しており、要件に合致すれば短期間で開設できる場合もありますが、資金の出し入れや信用面で総合銀行の口座を開けるなら開設しておくのが安心でしょう。
必要なライセンスや許可
シンガポールで事業を行う際、業種によっては事前に取得すべきライセンスや許可があります。以下に主要な例を挙げます。
飲食業: レストランやカフェを開業する場合、食品取扱免許(Food Shop License)や衛生許可が必要です。シンガポール食品庁(SFA)からの許可取得、店舗の衛生検査などのプロセスを経て営業開始となります。アルコールを提供する場合は追加で酒類販売免許も取得しなければなりません。
小売・流通業: 商品の輸入販売を行う場合、輸入許可(輸入申告)を税関(シンガポール関税局)で行う必要があります。特に医薬品、化粧品、化学物質、電子機器などは各主管庁(保健科学局HSAや情報通信メディア開発庁IMDA等)の認証・登録が必要な場合があります。また店舗を構える場合は看板の設置許可などローカルルールへの適合も求められます。
金融・フィンテック: 資金移動業、貸金業、資産運用、仮想通貨ビジネス等を行うには金融管理局(MAS)のライセンスが必須です。ライセンス要件として資本金の最低額や内部管理体制、役員の適格性など厳しい基準が定められており、取得までに相当の時間と費用がかかります。
その他規制業種: 建設業では建設局(BCA)への登録や現場監督資格者の配置が求められ、不動産仲介業では宅地建物取引業に相当する免許(CEA登録)が必要です。美容院・理髪店も保健環境省(NEA)の衛生基準遵守が求められます。このように業種ごとに所管官庁が定めるライセンスを確認し、早めに申請準備を進めましょう。
これら許認可取得には時間がかかることを念頭に置いてください。事業計画段階で必要なライセンスを洗い出し、シンガポール進出コンサルタントや政府機関に相談しながら進めると安心です。例えば飲食業の食品営業許可は通常数週間で取れますが、金融業のライセンスは半年以上かかるケースもあります。ライセンス取得が事業開始のボトルネックにならないよう、計画的なアクションが重要です。
まとめ
シンガポールでの会社設立は、ビジネスに適した環境とASEANの中心という戦略的な立地を活かせる魅力的な選択肢です。低い法人税や安定した法制度、政治環境に加え、アジアのハブとしての役割は、海外展開を目指す企業にとって利便性のある事業となる可能性を秘めています。その一方で、成功を収めるには、現地の規制や市場の特性を正しく把握し、計画的に準備を進めることが不可欠です。
シンガポールでの会社設立にあたり、本記事で紹介したポイントが参考になれば幸いです。