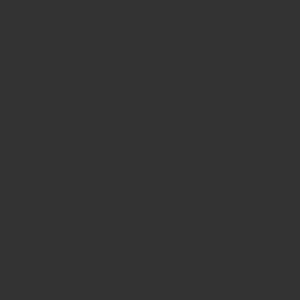現地で事業を始めるには「支店」「現地法人(Private Limited Company)」「駐在員事務所」のいずれかの形態を選択する必要があり、それぞれに特徴や要件があります。
本記事では、日本企業の経営者やスタートアップ創業者、個人起業家の方向けに、シンガポールで事業拠点を設立する方法とポイントを詳しく解説します。具体的なデータや事例を交えながら、各形態のメリット・デメリットや手続きの流れを比較し、目的に応じたベストな選択肢を考察します。
1. 支店設立(Branch Office)
概要(定義・特徴)
支店(Branch Office)とは、日本にある本社企業のシンガポールにおける海外支店です。シンガポールにおける支店は独立した法人格を持たず、本社と同一の法人とみなされます。そのため、支店の事業範囲は本社が行う事業内容の範囲内に限られ、本社の業務に準ずる活動しかできません。シンガポールでは一般的に現地法人の設立が好まれる傾向にありますが、それでも状況によって支店形態が選択されるケースもあります。支店は本社の一部として位置付けられるため、本社の信用力や実績を直接活用できる反面、独立性がない点が特徴です。
設立要件
シンガポールに支店を設立するには、本社企業に関する各種書類の提出や現地代理人の任命が必要です。主な要件は以下のとおりです。
- 本社と同一の名称で支店登記を行うこと(通常、「〇〇株式会社シンガポール支店」のような形で登録)。
- シンガポール居住者の代理人(現地責任者)を最低1名指名すること。この代理人は通常シンガポール在住の社員や役員、あるいはサービスプロバイダーのノミニーを充てます。
- シンガポール国内の登録住所を用意すること。バーチャルオフィスやサービスオフィスの住所でも登記は可能ですが、正式な住所が必要です。
- 本社の登記関連書類の提出: 本社の登記簿謄本や定款(英文翻訳・認証付)が必要です。また、本社取締役全員の氏名・住所・パスポート番号など、本社情報の開示も求められます。
- 会計年度の一致: シンガポール支店の決算期は、本社の会計年度に合わせる必要があります。支店は本社と別法人ではないため、決算期も連動させる決まりです。
さらに、支店設立後は本社の定時株主総会日から2ヶ月以内に以下の書類をシンガポール当局(会計企業規制庁:ACRA)へ毎年提出する義務があります。
– 支店の年次報告書
– 支店の監査済財務諸表(決算書)
– 本社の財務諸表(決算書)
本社が日本企業の場合、日本の決算書を英訳して提出する必要があります。以上のように、支店は設立時および設立後も本社に関する情報開示と報告義務が伴います。
税務・法務の詳細
法務面では、支店はシンガポールにおいて独立した法人ではないため、支店が負う債務や責任は最終的に本社(親会社)が無制限に負います。言い換えれば、支店で発生した債務不履行や訴訟リスクはそのまま日本の本社に及ぶ点に注意が必要です。有限責任のメリットがない代わりに、本社の事業として統合的に扱われます。
税務面では、支店がシンガポールで得た利益にはシンガポールの法人税(現行税率17%)が課されます。税率そのものは現地法人の場合と同じですが、支店の損益は本社の損益に合算され最終的に本社所在地国(日本)の課税対象にもなります。例えば、日本の本社がシンガポール支店で上げた利益は、日本の連結納税や外国税額控除の対象となり、日本の法人税率(約23〜30%)で課税される可能性があります。このため、シンガポール事業で利益が見込まれる場合、支店形態より現地法人化した方が税負担を抑えやすいとされています。逆にシンガポールで赤字が出た場合は、本社の損益通算により日本国内の課税所得を圧縮できるという側面があります(日本の税制上、海外支店の損失を本社の経費にできるケースがあります)。
また、支店はシンガポールでは非居住者扱いの外国法人とみなされるため、シンガポールの現地法人が利用可能な各種の税制優遇措置を受けられない場合があります。例えば、シンガポールでは新規中小企業向けの部分的な法人税免除や、一定条件下でのスタートアップ税控除措置がありますが、支店形態ではこうした恩恵を受けにくい点もデメリットです。法務面では、支店は本社の一部として法令遵守を求められ、現地会社法に基づき必要な報告・監査を行う義務があります。一方で、支店自体の清算時には清算手続(清算人の選任等)は不要で、登録抹消(ACRAへの支店閉鎖申請)をするだけで事業終了が可能です。この点は現地法人に比べ簡便です。
メリット・デメリット
メリット:
- 本社資源の直接活用: 支店は本社と同一法人のため、シンガポールでの事業に本社の資本金や信用力をそのまま活かせます。特に大規模プロジェクト入札時に本社の資金力・実績を示せる点は有利です。
- 資金移動が容易: 本社⇔支店間の資金のやり取りがシンプルです。現地法人の場合は増資や親子ローン手続きが必要ですが、支店であれば本社から必要な額を直接送金すれば足ります。迅速な資金供給が可能なため、大量の運転資金が必要な商社などでは利点となります。
- 本社との損益通算: シンガポール支店の損益を本社の会計に取り込めるため、グループ全体での税務計画が立てやすい側面があります。例えば支店の赤字を本社の黒字と相殺するといった調整が可能です。
- 撤退・清算の容易さ: 前述の通り支店閉鎖時は清算手続きが不要で、登記の抹消のみで終了できます。現地法人の清算に比べ時間・コストがかからず、柔軟に撤退判断を下せます。
- 設立可能な業種: ほとんどの業種で支店形態を取ることが可能です(一部規制業種を除く)。本社が営むビジネスであればシンガポールでも同様に展開できるため、新たな事業範囲を定める必要がありません。
デメリット:
- 本社へのリスク直結: 支店の債務や法的トラブルは本社が無限責任を負います。現地で何か問題が起きれば日本の親会社が賠償責任等を負う可能性があり、リスク隔離ができません。
- 設立手続きの煩雑さ: 現地法人に比べ設立手続きが複雑です。本社の定款英訳や公証、各種書類取り寄せなど準備事項が多く、時間と労力を要します。また、本社の取締役個人情報を開示する点に抵抗を感じる企業もあります。
- 事業範囲の制限: 支店は本社と同じ事業内容しか行えないため、例えば本社が手掛けていない新規事業をシンガポールで展開するといった柔軟性に欠けます。事業の自由度では現地法人に劣ります。
- 税務上の不利: シンガポールで発生した利益が日本本社の課税所得に加算されるため、せっかくのシンガポールの低税率メリットを享受しづらいです。さらに、シンガポールの優遇税制や補助金等も支店では利用不可の場合があります。結果としてトータルの税負担が増加する可能性があります。
- 現地での信用面: 一般的にシンガポールでは、現地法人の方が現地ビジネスパートナーや顧客からの受け入れが良い傾向があります(支店だと「外国企業の一部」という認識のため)。また、銀行口座開設等でも現地法人形態の方が手続きに融通が利く場合があります。
以上のように、支店形態は本社の延長として動ける反面、本社と表裏一体であるためリスクや制約も多い点を押さえておきましょう。
手続きの流れ
シンガポールで支店を開設する手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
- 事前準備: 日本本社にて支店設置の社内決議を行い、必要書類を準備します。具体的には本社の登記証明書や定款の英訳・認証、本社取締役会決議書(支店開設と現地代理人選任の承認)などです。これらを揃えるのに時間がかかるため、早めに着手しましょう。
- 現地代理人の選任: シンガポール居住者から支店の代理人となる人物を決めます。本社から駐在員を派遣する場合は、その者が就労ビザ(エンプロイメントパス等)を取得して現地に赴任します。現地に適任者がいない場合、法人サービス会社のNominee Agentサービスを利用することも可能です。
- 名称申請: 支店の名称をACRAに申請します。本社と同一名称での登録が原則ですが、既存の会社と重複しないか確認されます。名称予約は通常即日または数日以内に承認され、予約は2ヶ月有効です。
- 支店登記申請: ACRA(会計企業規制庁)のオンラインシステムから支店開設登記を申請します。提出書類一式をアップロードし、所定の登録料を支払います。申請が受理され問題なければ約1営業日で登記が完了します。登記完了後、ACRAから支店登録証明書(BizFile)の発行を受けます。
- 銀行口座開設: 支店名義の銀行口座を開設します。シンガポールの銀行は法人顧客の審査に慎重で、口座開設に数週間(通常3〜4週間)かかることもあります。事前に必要書類(本社の会社情報、支店登記証明、代理人の身分証明など)を準備し、銀行と面談を行います。
- 事業開始の準備: オフィスの契約やスタッフ採用を行います。支店は契約行為が可能なので、オフィスリース契約や現地採用社員との雇用契約を本社名義で締結できます。必要に応じて事業ライセンスの取得も行います(業種によって金融庁や各省庁への許認可申請が別途必要。
- 継続的なコンプライアンス: 毎年、本社および支店の財務諸表提出など所定の報告を怠らないようにします。また、年度末にはシンガポールで支店の法人税申告(Income Tax Return)を行います。会計監査も必要に応じて受け、本社と連携して決算処理を行います。
支店設立には本社側の準備と現地での手続きが並行して必要となり、現地法人設立よりも時間と労力がかかる傾向があります。しかし、書類さえ整えば登記自体は迅速に完了し得ます。専門の代行業者を利用することで手続きを円滑に進めることも可能です。
2. 会社設立(Private Limited Company)
概要(定義・特徴)
「会社設立」とは、シンガポール現地に子会社となる法人を新たに設立することを指します。具体的には、日本でいう株式会社に相当する有限責任会社(Company Limited by Shares)をシンガポールで設立する形態が一般的です。現地法人は日本の親会社から法的に独立した存在であり、シンガポールの会社法上独立した法人格が付与されます。そのため、親会社とは異なる事業であってもシンガポールで自由に展開可能で、事業内容に制限は基本的にありません。実務的にも、シンガポールは会社設立手続きが他国に比べ容易で、税制上の恩恵も受けられることから、日系企業の進出形態として最も一般的なのが現地法人の設立です。
シンガポールの有限責任会社は、名称の末尾に”Private Limited”(略して”Pte. Ltd.”)を付す形で登記されます。株主の出資額を限度に責任を負う有限責任構造のため、親会社にとってはリスクを限定できるメリットがあります。また、一つの現地法人内で複数の事業ライセンスを取得して幅広いビジネスを行うことも可能です。
設立要件
シンガポールで現地法人(Private Limited Company)を設立するには、以下の要件・条件を満たす必要があります。
- 最低1名の株主: 個人または法人いずれも株主になれます。100%外国資本(日本企業単独出資)でも設立可能で、現地資本との合弁も自由です。株主数は50名以下である必要があります(51名以上になると公開会社扱い)。
- 取締役(Director): 少なくとも1名はシンガポール居住者であることが法定要件です。居住者とはシンガポール国民や永住者(PR)、または就労ビザ保有者を指します。それ以外に取締役は外国在住者でも就任可能です。取締役会を組織し、会社経営の責任者となります。
- カンパニーセクレタリー(Company Secretary): 会社設立後6ヶ月以内に、シンガポール居住の会社秘書役を選任する必要があります。秘書役は会社法上の文書管理や当局対応の責任者で、外部の専門職に委任するケースが多いです。
- 登録住所: シンガポール国内の登記上の本店住所が必要です。商業用オフィスの住所が望ましいですが、規制を満たせば自宅住所を登記することも可能です(ただしバーチャルオフィス利用時は当局認可済み住所であることを確認)。
- 最低資本金: 資本金(払込資本)の最低額は1シンガポールドルから設定できます。実務上は初期運転資金に応じ数千〜数万ドル程度を資本金として払込みますが、法的には1ドルで設立可能です。資本金額が会社の対外的信用力にも関わるため、日本企業の場合は目安として5-10万SGD程度を払い込むことが多いです。
- 親会社の書類: 親会社が株主となる場合、日本の商業登記簿謄本や定款の英訳など出資母体の情報提出が必要になります。個人株主の場合はパスポートや住所証明などKYC書類の提出が求められます。
以上が主な法定要件です。加えて事業内容によっては別途ライセンス取得要件があります。例えば金融業、保険業、教育サービス等は所管官庁の許認可が必要となります。しかし基本的にシンガポールは外資規制が緩和されており、ほとんどの業種で現地法人の設立・営業が可能です。
税務・法務の詳細
法務面: 現地法人はシンガポール法に基づき設立された独立法人であり、親会社とは別個の権利義務主体です。したがって、現地法人の債務に対する責任は会社自身の資産をもって弁済される範囲に限定され、親会社や株主個人に及ぶことは原則ありません(有限責任)。これは万一現地法人が倒産しても、親会社の資産は守られることを意味します(ただし親会社が保証人となった借入れ等は除く)。また現地法人は独自の社名・ブランドで活動でき、契約も現地法人名義で締結します。シンガポール会社法に従い取締役会・株主総会を運営し、年次の財務報告や監査義務を果たす必要があります。
税務面: シンガポール現地法人の所得はシンガポールで課税対象となり、法人税率は一律17%です(2025年現在)。しかし、シンガポールには中小企業向けの部分的税率軽減措置があり、新規設立企業や小規模企業の場合、最初のS$200,000程度の課税所得について一部税率が軽減されます。また、一定の要件を満たす企業は法定監査が免除される制度もあります。具体的には、グループ全体で売上高が1,000万Sドル以下・総資産1,000万Sドル以下・従業員50人以下のうち2項目を満たす場合、監査不要となります。これにより小規模現地法人は監査費用を省けます。
シンガポール現地法人は税務上シンガポール居住者となるため、日本との間で締結されている租税条約上の恩恵も享受できます。例えば、日本親会社への配当はシンガポールで源泉徴収税0%(非課税)で送金可能です(日星租税条約に基づく)※。また、日本の税制では海外子会社から受け取る配当の95%相当額が益金不算入(非課税)となるため、現地法人の利益を日本に戻す際の二重課税もほぼ排除されています。こうした点からも、シンガポールで得た利益を低税率のままグローバルで活用しやすいメリットがあります。
※注: 2019年改正の日星租税条約により、シンガポール子会社から日本親会社への配当は持株割合要件を満たせば源泉税0%となっています。
一方、親会社から見れば現地法人は別会社のため損益通算はできません。現地法人が赤字でも日本本社の税負担を軽減することはできず、黒字でも本社に直接課税されない代わりに利益留保は現地法人内に留まります。出資した資本金の範囲でしかリスクを取らない一方、初期投資額以上の損失が出た場合は現地法人を清算するかたちで処理することになります。
メリット・デメリット
メリット:
- 親会社のリスク限定(有限責任): 現地法人は独立した会社であり、万一失敗しても親会社の損害は出資額に限定されます。本社の資産を守りつつ海外展開ができるため、日本企業にとって安心感があります。
- 事業運営の自由度: シンガポール現地法人は事業目的に制約がなく、親会社の本国事業と異なる分野にも進出可能です。例えば日本では製造業だがシンガポールでは販売会社を営む、といった柔軟な展開ができます。また、社名も自由に決められブランド戦略を現地に適した形で行えます。
- 税制優遇と低税率: シンガポールの低い法人税率(17%)の恩恵を直接受けられる他、創業免税措置や各種インセンティブを活用できます。結果としてグローバルで見た税引後利益の最大化を図りやすいです。特に一定の条件を満たせば数年間は実効税率がさらに下がる制度もあります。
- 信用力の構築: 現地法人として登記されていることで、シンガポール国内の取引先や政府機関から信頼を得やすくなります。入札参加や営業許可の申請時にも「シンガポール企業」として対応され、有利に働く場面があります。銀行融資や助成金申請も現地企業ならではの選択肢が増えます。
- 柔軟な資本政策: 現地法人は必要に応じて増資や新規株主の受け入れが可能です。将来的に第三者から資本調達したり、現地パートナーと合弁化したりといった選択肢が取れます(支店ではこれができません)。スタートアップであれば現地で投資家から出資を受けることも可能です。
- 長期的な継続性: 駐在員事務所と異なり期間制限なく事業を継続できます。親会社の戦略次第で長期にわたりシンガポール拠点を運営でき、規模拡大も自由です。
デメリット:
- 設立・維持に一定のコスト: 会社設立時に登記費用(ACRA登録料S$300)や専門家への依頼費用が発生します。また、毎年の会計・税務申告や場合によっては監査など維持費用もかかります。清算する際も清算人の選任や公告手続きなどコストと手間がかかります(ただし一定条件で簡易な抹消も可能)。
- 現地役員の確保: 居住取締役や会社秘書役を確保する必要があります。信頼できる人材がいない場合、プロフェッショナルサービスに依頼することになりますが、これにも年間費用がかかります。役員要件を満たさないと設立できない点はハードルです。
- 資金移動の手続き: 親会社から現地法人への資金援助は増資や親子ローンといった正式手続きが必要です。支店のように自由に本社資金を使えないため、迅速な巨額資金投入が求められる事業では不便な面があります。また、親子ローンの場合は適正金利や為替リスクにも注意が必要です。
- 親会社との損益相殺不可: 現地法人の損失は親会社の利益と相殺できず、スタートアップ期に赤字が出ても日本本社の節税には寄与しません。黒字の場合はシンガポールに利益が留まり、本社が直接使うには配当などの手続きが必要です。
- 撤退時の手間: ビジネスを終了する際、現地法人は清算または登記抹消の手順を踏む必要があります。清算には数ヶ月~1年程度かかるケースもあり、支店のように短期間で撤退とはいきません。また清算時には債務整理や税務調査が行われることもあります。
以上を踏まえると、現地法人設立は初期コストこそかかるものの、独立した拠点として長期的・主体的に事業を展開するのに適した形態と言えます。日系企業の多くはこのメリットを重視し、シンガポール進出時に現地法人を選択しています。
手続きの流れ
シンガポールで現地法人(Private Limited)を設立する手続きの一般的な流れを説明します。
- 会社名の決定と予約: 希望する会社名を決め、ACRAのオンラインシステムで商号を予約します。名前は英語で付ける必要があり、既存の会社名と重複しないことや、不適切な単語が含まれないこと等が審査されます。予約申請は通常即日〜1営業日で承認され、承認後2ヶ月間その名称は確保されます。
- 定款(Constitution)の作成: シンガポール会社の定款を準備します。定款には会社名、事業目的、株式資本の構成、取締役・株主の権限などを定めます。一般的には政府提供の雛形(Model Constitution)を基に作成しますが、親会社の意向に合わせて事業目的を広めに記載するなど調整します。
- 設立登記(Incorporation)の申請: ACRAに対しオンラインで会社設立登記を申請します。手続きは高度に電子化されており、所定フォームに会社情報(本店住所、事業内容、資本金額、株主・取締役リストなど)を入力します。株主や取締役になる個人・法人のKYC情報や身分証もアップロードします。内容に不備がなければ申請後数時間〜1日程度で設立登記が完了し、BizFile(電子登記証明)が発行されます。同時に会社登録番号(UEN)が付与されます。
- 初回取締役会・株主総会: 会社設立後、可能な限り早期に最初の取締役会を開催します。ここでは会社秘書役の正式任命、銀行口座開設の承認、会計期間の決定など初期の重要決定を行います。また必要に応じて創立総会(株主総会)で定款承認や取締役選任の追認を行います。
- 法定登録事項の完了: 設立から14日以内に所在地住所の掲示(看板設置)や、株式発行の登録、株券発行(現物発行は任意)など会社法上の要件を満たします。会社秘書役を6ヶ月以内に任命し、雇用法関連ではCPF(中央積立基金)や社会保険等の事業者登録も行います。
- 銀行口座の開設: シンガポール国内銀行にて会社名義の銀行口座を開設します。KYC審査があり、取締役や実質的支配者(Ultimate Beneficial Owner)の情報提出が求められます。審査と手続きに約3〜4週間かかることが一般的です。必要に応じ、日本のメガバンクのシンガポール支店など日系行を利用するケースもあります。
- ビザ申請・オフィス開設: 日本から派遣する駐在員の就労ビザ(Employment Pass等)の申請を行います。会社設立が完了していることが前提となるため、設立後に速やかにオンラインで申請を進めます。同時にオフィスの賃貸契約や現地スタッフの採用手続きを進め、営業開始の準備を整えます。
- 各種許認可の取得: 業種によって必要となる営業許可やライセンスを取得します(金融業ならMASへのライセンス申請、飲食業なら保健所の許可など)。一般的なコンサルティングや貿易業であれば特別な許認可なしで営業可能です。
- 事業開始: 以上のステップを経て、実際に売上計上する事業活動を開始します。以降は毎年の決算・納税や株主総会を実施し、法令遵守に努めながら事業を運営します。
シンガポールの会社設立手続きはオンラインで完結し、非常に迅速かつ簡便です。必要書類さえ揃えば設立自体は1日で完了するため、早ければ数週間以内に事業を開始できます。もっとも、銀行口座開設やビザ取得には時間を要するため、実働開始まで1〜2ヶ月程度見込んでおくと良いでしょう。
シンガポールは世界銀行の「ビジネスのしやすさ」ランキングで常に上位に入るほど起業しやすい国です。 安定した経済環境と低い法人税率(17%)などの優遇された税制により、多くの外国企業にとって魅力的な拠点となっています。 本記[…]
3. 駐在員事務所(Representative Office)
概要(定義・特徴)
駐在員事務所(Representative Office、略称RO)とは、親会社の現地連絡事務所のような位置付けであり、市場調査や情報収集など限定された活動のみを行う拠点です。駐在員事務所自体はシンガポールで法人登録されるものではなく、独立した法人格を持ちません。あくまで親会社の一部門として存在し、営利を目的とする事業活動は一切認められていない点が最大の特徴です。
具体的に、駐在員事務所が許される活動は市場調査、現地のビジネス環境や法規制調査、現地での広報・情報収集、展示会出展などに限られます。営業行為や契約締結、商品・サービスの販売、アフターサービス提供などは行えません。駐在員事務所を設立する目的は、本格的に現地法人や支店を設ける前段階として、事業可能性を探るフィージビリティスタディを行うことにあります。そのため長期的な存続は想定されておらず、通常1年単位で設置が認められ、最大でも更新を含めて3年程度で現地法人か支店への移行か撤退かの決断を迫られます。
駐在員事務所には法人格がありませんが、設置することで駐在員用の就労ビザ(Employment Pass)の取得が可能となり、現地で事務所スペースや社宅を契約する法的根拠が得られます。つまり、駐在員事務所を開設すれば日本から社員を派遣して駐在させることができ、オフィスを構えて活動拠点とすることができます。ただしそこで行えるのはあくまで非営利活動のみという点に注意が必要です。
設立要件
駐在員事務所をシンガポールに設置するには、親会社が一定の要件を満たしている必要があります。Enterprise Singapore(シンガポール企業庁、旧称IE Singapore)が定める基準によれば、親会社の売上高が少なくともUS$25万(約3,000万円)以上であること、および設立後3年以上経過した企業であることが条件とされています。新興のスタートアップや売上規模の小さい企業は駐在員事務所として認可されない場合があるため注意が必要です。
また、駐在員事務所にはスタッフ数の上限もあります。駐在員事務所で勤務できるスタッフは5名未満と定められており、小規模な調査拠点としての性格が維持されます。通常、親会社から派遣される駐在員(現地駐在代表者)1名と、必要に応じて数名のローカルスタッフで構成されます。
その他の必要条件・書類は以下のとおりです。
- 親会社の最新の事業概要: 過去3年間の年次報告書や財務諸表(英語版)が必要です。未上場企業の場合は直近の監査レポート等も提出します。
- 駐在員事務所の所在地: シンガポールで活動するオフィス住所を確保します。サービスオフィスなどでも差し支えありませんが、正式な連絡先となります。
- 現地駐在員の指名: 親会社から派遣する駐在員(Chief Representative)を決定します。通常、日本人社員をEP取得の上で現地駐在させ、その者が駐在員事務所の代表となります。
- 申請先: Enterprise Singaporeに申請を行います(金融・銀行業の場合は金融通貨庁MASが管轄)。申請書には親会社の情報、シンガポールで行う活動内容、駐在員情報などを記載します。
以上の書類を揃え、当局の承認を受けることで駐在員事務所を開設できます。承認後は正式に「Representative Office」として活動開始となり、駐在員の就労ビザ申請手続きも可能になります。
税務・法務の詳細
法務面: 駐在員事務所はシンガポールの法律上「事業体」ではなく、契約主体にはなり得ません。従って、駐在員事務所名義で商取引契約を締結することはできず、必要があれば親会社本体が契約当事者となる形をとります。また、駐在員事務所そのものは登記上存在しないため、会社法の規制(取締役の設置や年次報告など)の対象外です。ただし、駐在員事務所として許可された活動範囲外の行為(例えばこっそり営業活動をする等)を行うと許可取り消しや罰則の対象となるため、運用には注意が必要です。親会社は駐在員事務所で行われる活動の結果に対して全責任を負います。例えば市場調査中に何らかの債務や損害が発生した場合、それは親会社の責任として扱われます。
税務面: 駐在員事務所は収益を上げる事業活動を行わないため、シンガポールでの課税所得を生み出しません。したがってシンガポール国税庁への法人税申告義務もなく、税務上は課税対象外となります(収入がないため)。売上や利益が出せない代わりに、現地での会計帳簿も簡易な管理で済みます。またGST(物品サービス税=消費税)の登録も不要です。要するに、駐在員事務所は親会社のコストセンターであり、発生する費用(駐在員給与、事務所賃料など)はすべて親会社負担となります。親会社の税務上は、それら費用を海外事業調査費等として計上する形になります(日本の税法上一定額まで損金算入可能な場合あり)。
メリット・デメリット
メリット:
- 低コスト・低リスクで市場調査: 駐在員事務所は法人設立に比べてコストが圧倒的に低く抑えられます。登記費用も不要で、年次の監査や税申告もありません。必要なのはオフィス維持費と人件費程度で、維持管理費用が低く管理も簡便です。そのため「まずは市場調査だけ」「現地の様子見」という段階での進出手段として最適です。失敗しても撤退コストがほぼかからないため、リスクを最小限にできます。
- スピーディな設置: 必要書類(親会社の財務資料等)が揃っていれば、駐在員事務所の申請から承認までのプロセスは比較的迅速です。会社設立のような複雑な手続きがないため、短期間で現地に拠点を構えることができます。承認後はすぐに駐在員を派遣でき、現地活動を開始できます。
- 柔軟な撤退: 駐在員事務所は期間が限定されているため、延長しなければ自然消滅します。撤退する際も清算等の手続きは不要で、単純に拠点閉鎖するだけです。将来本格進出しないと判断した場合でも、容易に現地から手を引けます。
- 就労ビザの発給が可能: 駐在員事務所を設立すると、親会社の社員をシンガポールに駐在員(Representative)として派遣できます。この社員には就労ビザ(Employment Pass)が発給され、合法的に長期滞在し活動することができます。現地法人を作らずとも人材を送り込める点は、市場開拓のための大きなメリットです。また必要なら現地で少数のローカルスタッフを雇用することもできます。
- 現地拠点のプレゼンス確保: たとえ営業活動不可でも、現地に「〇〇社シンガポール駐在員事務所」と看板を出し連絡先(住所・電話)を持てること自体に意味があります。展示会出展や現地ネットワーキングにおいて、拠点なしの状態より信頼感を与えることができます。
デメリット:
- 収益活動ができない: 駐在員事務所最大の欠点は一切売上を上げられないことです。契約締結や受注・請求行為、金銭の授受などビジネスに直結する行為は全て禁止されています。そのため、どんなにビジネスチャンスが目の前にあっても、駐在員事務所のままでは取引を開始できません。商談が具体化した段階で現地法人や支店を設立し直す必要があります。
- 設置期間に制限: 駐在員事務所は原則1年ごとの更新制で、通常最長でも3年程度しか存続が認められません。つまり一時的な準備拠点としての位置づけであり、長期に居座ることは想定されていません。この期間内に現地法人化か撤退かの判断を迫られるため、猶予が限られます。ダラダラと調査を続けることはできず、タイムリミットがある点はプレッシャーとなります。
- 親会社の規模要件: 前述の通り、駐在員事務所を設置するには親会社が一定の規模(売上・設立年数)を満たしている必要があります。設立まもないベンチャー企業などは駐在員事務所という選択肢自体が取れない場合があります。その場合、最初から現地法人を作るしかありません。
- 活動範囲の制約: 情報収集や市場分析といった裏方業務しかできないため、駐在員事務所で得た知見を実践に移すには組織変更が必要です。また、駐在員事務所名義ではオフィス契約や宣伝広告の実施にも制限があり、実務上すべてを親会社名義で行う必要がある場面もあります。ビジネス上の主体として動けない不自由さがあります。
- 信用・採用面での限界: 駐在員事務所は所詮仮の拠点であるため、優秀な人材を現地採用する場合に「正式な法人ではない」点を不安視されることもあります。また取引先からしても「まだ本格進出ではないのだな」と受け取られるため、大きな商談には繋がりにくい側面があります。
総じて、駐在員事務所は短期的な市場参入準備には適していますが、それ自体が事業の収益拠点となることはありません。期間限定のリサーチ拠点という割り切った使い方が求められます。
手続きの流れ
駐在員事務所開設の手続きは他の形態に比べれば簡易ですが、概略を示します。
- 親会社内での決議: まず日本本社側で駐在員事務所設置の決裁を取ります。駐在員の選定や予算措置を決めておきます。
- 必要書類の収集: 親会社の直近3年分の監査済決算書・年次報告書(英文)を用意します。会社案内や事業内容説明資料も英文で整備します。
- 申請書の作成: Enterprise Singaporeの定める駐在員事務所申請書フォームに必要事項を記入します。親会社の基本情報(会社名、所在地、代表者など)、売上高や従業員数、シンガポールで予定する活動内容、派遣予定の駐在員氏名・役職などを記載します。
- 当局へ申請: Enterprise Singapore(一般企業の場合)またはMAS(金融関連の場合)へオンラインまたは指定の方法で申請を提出します。申請料が必要な場合は支払い、受理後審査を待ちます。審査期間は数日から数週間程度です。基準を満たしていれば概ね承認されます。
- 承認・登録: 承認されると駐在員事務所の登録証明が発行されます。これにより正式に駐在員事務所として活動開始が可能です。承認通知には駐在員事務所の登録番号や有効期限(1年)が記載されます。
- 就労ビザ取得: 親会社から派遣する駐在員について、シンガポール人材庁へ就労ビザ(通常はEmployment Pass)の申請を行います。駐在員事務所登録証明や親会社の財務資料、駐在員の職務経歴書などを添付します。審査に数週間かかりますが、許可されれば駐在員はシンガポールで勤務可能となります。
- オフィス開設: 現地で事務所スペースを契約し、電話やインターネット回線を開設します。駐在員事務所の看板も掲げます。銀行口座については駐在員事務所単独では開設できないため、必要なら親会社名義で海外口座を開設するか、日本本社から経費送金で対処します。
- 活動開始: 駐在員事務所として市場調査やネットワーキング活動を開始します。現地の商工会議所やJETROなどに登録し情報収集する企業も多いです。活動の成果を親会社に報告しつつ、本格進出の是非を検討します。
- 更新 or 次のステップ: 1年経過前に引き続き駐在員事務所を継続する場合は、Enterprise Singaporeへ更新申請を行います。最新の親会社情報を提出し、もう1年活動延長する許可を得ます。最大で3回程度更新可能ですが、最終的には現地法人化か撤退かを決断します。
以上が駐在員事務所設立の流れです。全体として、他の形態に比べ手続きはシンプルで時間もかからない印象です。とはいえ期間満了までには次のアクションが必要になるため、計画的に活用しましょう。
4. 比較表:どの形態を選ぶべきか
上述した支店・現地法人・駐在員事務所の特徴を主要な観点で比較すると以下のとおりです。
表を見ると、それぞれの形態が何を優先するかによって向き不向きが分かれることがわかります。以下に、目的別にどの選択肢が適しているかを考えてみましょう。
目的別のおすすめの選択肢
- まずは市場調査をしたい場合: 現時点で具体的な事業プランや顧客がなく、「とりあえず現地のマーケットを知りたい」「将来の進出可能性を探りたい」という段階なら、駐在員事務所(RO)がおすすめです。駐在員事務所は低コストでリスクも小さく、状況に応じてすぐ撤退も可能なので、トライアル拠点として最適です。特に親会社が十分な規模であれば、ROを設けて日本人駐在員を派遣し、1〜2年かけて現地ネットワーク作りや市場分析を行うのは有効です。将来本格展開する際の土台づくりになります。ただし最大3年で区切りが来るため、それまでに次の戦略を固める必要があります。
- 早期に事業を開始したい・収益を上げたい場合: すでにシンガポールでのビジネス計画や顧客見込みがあり、現地で売上を立てたい場合は、現地法人(Pte Ltd)の設立が基本となります。営業活動や契約行為が必要なら駐在員事務所では不可能なので、迷わず現地法人を立ち上げるべきです。シンガポール現地法人は設立も簡単で1日で登記が完了するほどです。また日系企業の進出形態として実績も豊富で、信頼性や税制面のメリットも大きいです。スタートアップ創業者の場合、自社がまだ日本国内で法人化していないなら、直接シンガポールで法人を創る選択肢もあります(ただし現地のネットワークが乏しい場合は注意)。
- 本社の看板を活かしたい場合: 親会社が大企業でグローバルブランド力があり、その信用をフルに使ってビジネスをしたい場合や、親会社の財務力・実績を示すことが要求される事業(例: 大規模インフラ案件入札、金融ライセンス取得等)の場合は、支店形態が適していることがあります。支店であれば相手方に「〇〇株式会社のシンガポール支店」として本社そのものの一部だと認識してもらえるため、信頼や安心感を与えやすい場面があります。例えば、日本本社が建設業で資本金数十億円規模の場合、シンガポールでの建設プロジェクト入札に支店として参加すれば、本社の資本力をそのまま提示できます。現地法人を設立した場合、資本金はせいぜい数百万〜数千万円規模になりがちで、見劣りする可能性があります。同様に、銀行・証券など金融業では、本社の長年の実績がライセンス許可に有利に働くため、まず支店として進出する例も見られます。もっとも、支店を選ぶケースは特殊であり、多くの場合は現地法人で十分対応可能です。
- コストとリスクを極力抑えたい場合: 新規進出にあたり「なるべくお金をかけたくない、失敗時の損失も最小限にしたい」という保守的な戦略なら、やはり駐在員事務所が有力です。現地法人ですと設立・維持に数百万円単位のコストがかかるのに対し、駐在員事務所は駐在員の人件費と小さな事務所費用程度で済みます。売上ゼロでも本社の費用科目で処理でき、万一撤退しても清算損失は発生しません。リスクを限定しつつ様子を見るには最適ですが、その間にビジネスチャンスを逃す可能性もある点は認識しておきましょう。
- 将来の展開・柔軟性を重視したい場合: 現地でビジネスが軌道に乗った後の拡大や、第三者からの出資、他国展開へのステップなど将来の自由度を考えると、現地法人一択となります。現地法人なら事業内容変更や複数事業の平行展開もできますし、子会社を作ることもできます。支店の場合、親会社の事業範囲に縛られますし、新たなパートナー参入(資本参加)は構造上できません。駐在員事務所はそもそもビジネス開始ができません。したがって、中長期で見てシンガポール拠点を成長させたいなら現地法人設立がベストです。
以上をまとめると、短期の試行や情報収集には駐在員事務所、本格的な事業には現地法人、親会社の特殊な利点を活かすなら支店という使い分けになります。多くの日本企業はまず駐在員事務所から始め、現地の感触を掴んだら現地法人を設立するパターンを辿ります。あるいは初めから現地法人を設立し、ビジネスのスタートダッシュを図るケースもあります。また、一旦支店として進出し、その後現地法人に組織転換することも不可能ではありませんが、銀行口座を切り替えたり就労ビザを取り直したりと煩雑になるため、最初から形態選択は慎重に行うのが望ましいです。
5. まとめとアドバイス
シンガポールでの事業拠点設立について、支店・現地法人・駐在員事務所の特徴を見てきました。最後にポイントを整理し、成功する進出のためのアドバイスを述べます。
- 支店は本社の延長として活動できる形態で、本社のブランド力や資金力を前面に出したい場合に有効です。しかし親会社へのリスク波及や税務上の非効率を招くため、特別な理由がない限り日系企業の一般的な選択肢とは言えません。選ぶ場合は、本社と一蓮托生になる覚悟と、本社側での管理体制強化が必要です。
- 現地法人(子会社)は、シンガポール進出の王道パターンです。独立した会社として現地で信用を築きやすく、事業展開の自由度も高いため、長期的に見て最も柔軟で安定した形態です。初期費用や管理コストはかかるものの、シンガポールのビジネス環境(安定した法制度・低税率)をフルに活用できます。多くの日本企業にとって最善の選択肢は現地法人設立であり、実際その例が圧倒的多数です。
- 駐在員事務所は、まずマーケットテストしたい場合の一時的手段として有用です。低コスト・低リスクで海外拠点を持てますが、ビジネスは開始できないため、成果が出たら速やかに次の段階(法人化)に移行する計画を持ちましょう。ずるずると調査だけを続けるのは得策ではなく、3年程度を目処に本格展開か撤退かを判断する必要があります。
アドバイス: シンガポール進出にあたり重要なのは、初期段階で自社の目的や計画に合致した形態を選ぶことです。途中で形態を変更することも可能ですが、例えば「最初支店→後で現地法人へ変更」といった場合、銀行口座を再度開設したり許認可を取り直したりと手間が増えます。できるだけ最初の設立形態で将来まで見据えた運用ができるよう、入念に検討しましょう。各形態のメリット・デメリットを踏まえ、自社のビジネスモデル・リスク許容度・投資予算に照らして最適解を選ぶことが肝心です。
また、シンガポールでの会社設立や支店開設は手続き自体は簡便とはいえ、現地の法律や商習慣に精通した専門家のサポートを得るのがおすすめです。信頼できる現地の会計事務所やコンサルティング会社、あるいはJETROなど公的機関を活用し、最新の情報に基づいて進めてください。特に会社設立後の年次報告・税務申告・労務管理などコンプライアンス面は日本とは異なる部分も多いため、プロの助言を受けると安心です。
さいごに
シンガポールの進出にあたって、適切な組織形態を取ることが重要です。
各形態のメリット・デメリットの参考になれば幸いです。